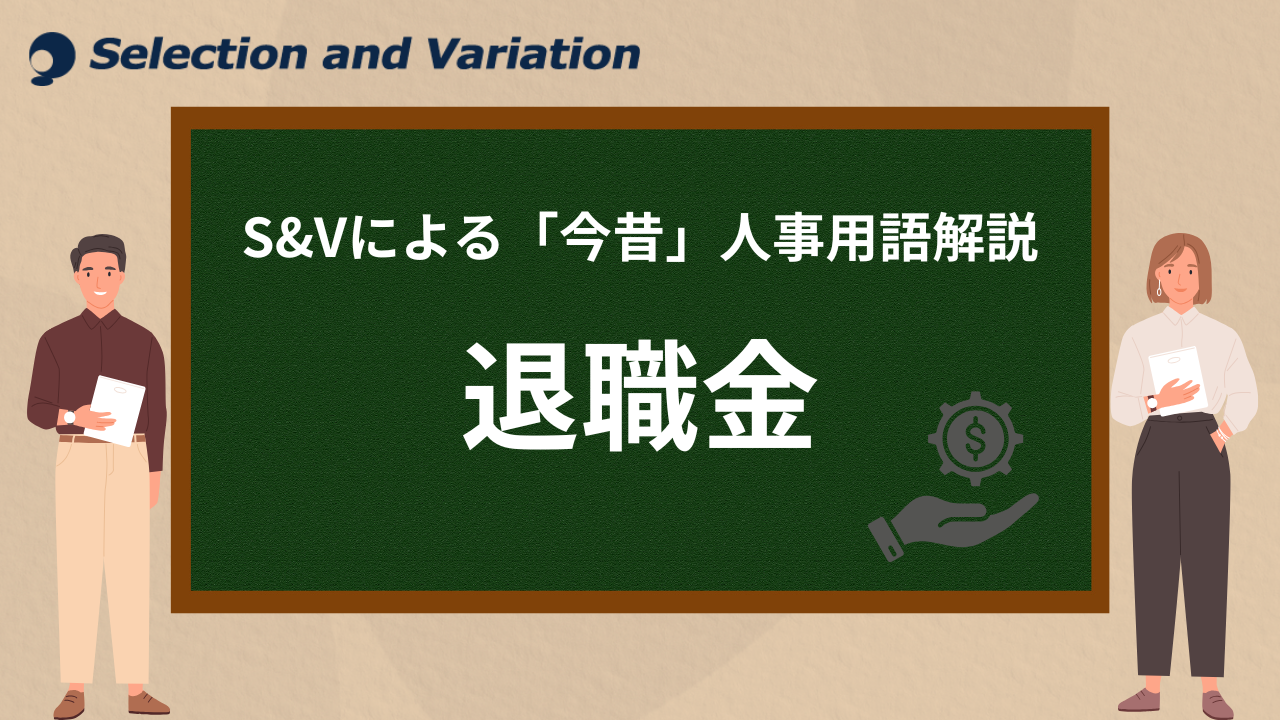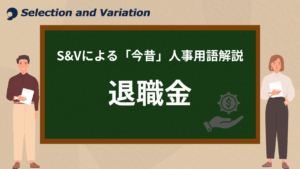平康 慶浩(セレクションアンドバリエーション株式会社 代表・人事コンサルタント)
人事制度の見直しの中で、議論が重くなりやすいテーマの一つが退職金です。
「うちはもう終身雇用ではないのに、退職金は必要でしょうか」
「若手には響かないのではありませんか」
そんな問いを、経営者や人事の方からよく投げかけられます。
一方で、制度改定の話を進めようとすると、社内からは強い不安や反発の声が上がることも少なくありません。
それだけ退職金は、単なるお金の話ではなく、働く人の人生観や会社との関係性 に深く結びついた制度だと言えます。
今回は、退職金の今昔を振り返りながら、令和の時代において企業がどのように向き合うべきかを考えてみたいと思います。
昭和:退職金は「終身雇用契約の完成形」だった
昭和の退職金は、今とはまったく違う意味を持っていました。
それは「長く勤め上げたことへの報償」であると同時に、終身雇用という約束を完結させる制度 だったのです。
昭和の退職金が担っていた役割
- 長期勤続への報奨
→ 勤続年数が長いほど金額が大きくなる設計。 - 老後生活の原資
→ 公的年金だけでは不十分な時代、退職金は生活設計の助けだった。 - 離職抑制の装置
→ 「辞めると損をする」仕組みとして機能。 - 企業と社員の信頼関係の象徴
→ 会社に人生を預ける代わりに、最後にまとまった対価が支払われる。
当時は、退職金があること自体が「良い会社」の証であり、賃金は月例給と賞与だけでなく、最後にもらう退職金まで含めて一つ、と考えられていました。
ちなみにこの場合の退職金はほとんど、確定給付型、といわれるものでした。よくある計算方法は、定年時の基本給×勤続年数に応じた係数をかけあわせる、というもので、だから評価を反映して減給してしまうのは、退職金にも影響があるから許されない、という制度改定への反論などもあったりしました。
平成:退職金は「重たい制度」として見直しの対象になった
平成に入ると、この前提が少しずつ崩れていきます。
終身雇用が揺らぎ、転職が珍しくなくなったことで、退職金の意味も変わり始めました。
平成に顕在化した課題
- 勤続年数前提が現実と合わなくなる
→ 中途入社が増え、退職金の格差が拡大。 - 企業側の毎年の負担がきつい(計上していない会社にとってはリスク)
→ 将来支払う金額がバランスシート上のリスクになる。 - 若手社員にとっては実感が薄い
→ 何十年先の話で、モチベーションに結びつきにくい。 - 成果主義・職務給との整合性が弱い
→ 「成果で報いる」考え方と相性が良くない。
そのため、多くの企業で次のような動きが見られました。
- 退職金の前払い給与化:
→ 大手企業を中心に、毎月計上している退職金算定基礎額、という金額をそのまま給与に上乗せするような取り組みをとる会社も。大手電機メーカーだと、1年目社員でも10万円以上の毎月加算になることも(これは数年で廃止されたらしいですが) - 退職金算定方法の見直し:
→ ポイント制のように、毎年あるいは毎月対処金相当額を積み上げる計算方法を導入。成果主義人事などで、定年時の給与が必ずしも一番高い、という状況ではなくなった企業では必須の対応でした。 - 確定拠出年金(DC)への移行:
→ 上記のように、都度払いに変えるのなら、それを会社が預かって運用する、という形式よりも、そもそも個人に渡してしまった方が良いのでは、という考え方に基づく仕組み。税務的な優遇措置から、60歳が来るまで引き下ろせないようなことが一般的。かつ、DC導入企業同士なら、会社が変わってもそのまま持っていけるような仕組みも。
このように、退職金は、「あって当たり前の制度」から維持するかどうかを検討すべき制度 へと位置づけが変わっていったのです。
令和:退職金は「人生設計をどう支えるか」という問いに変わった
令和の退職金議論は、単なるコスト削減や制度廃止の話ではありません。
むしろ焦点は、「企業は社員の人生にどこまで関与するのか」 という点に移っています。
令和の退職金をめぐる現実
- キャリアは一社完結ではない
- 定年後も働き続ける人が増えている
- 老後資金の考え方が多様化している
こうした環境の中で、退職金は次のように再定義されつつあります。
現代的な退職金の捉え方
- “老後資金”ではなく“長期的な報酬の一部”
- 一時金ではなく、積立・運用を前提とした制度
- 企業が保証するのではなく、社員が主体的に選択する仕組み
その象徴が、前述した確定拠出年金(DC)です。
DCは、企業が掛金を拠出し、運用は個人が行う制度であり、「会社が面倒を見る」から「会社が機会を提供する」 への転換を表しています。
退職金を見直す企業が直面する“感情の壁”
退職金の議論が難しい理由は、金額以上に 感情的な要素 が大きいためです。
よくある社内の反応
- 「会社に長く貢献してきた意味がなくなるのでは」
- 「約束を反故にされた気がする」
- 「これまで我慢してきたのに、最後に削られるのか」
退職金は、社員にとって“会社との関係性の総決算”のように受け止められがちです。
そのため、制度を見直す際には、
- 一律廃止ではなく段階的に
- 既存社員と新規採用者で区分
- 代替制度(給与・DCなど)を明示
といった慎重な対応が欠かせません。
これからの退職金設計で考えるべきポイント
令和の退職金は、「残すか・なくすか」という二択では語れません。
重要なのは、自社の人材戦略とどう結びつけるか です。
設計のための視点
- 長期定着をどこまで重視するか
→ 定着重視なら退職金は有効な装置。 - 報酬の透明性をどう確保するか
→ 将来給付より、見える報酬を重視する層も多い。 - 職務給・市場価値給との整合性
→ 月例給とのトレードオフ設計が必要。 - 社員の金融リテラシー支援
→ DC導入時は教育とセットで。 - 企業文化との相性
→ “最後まで面倒を見る”文化を残すのかどうか。
退職金は制度設計以上に、企業が社員とどんな関係を築きたいかを映し出します。
おわりに:退職金は“企業と社員の関係性の集大成”
昭和において退職金は、終身雇用の完成形でした。
平成には、その重さと不確実性が課題となり、令和では、人生設計をどう支援するかという問いへと変わっています。
退職金は、もはや「当然ある制度」でも「単に廃止すべき制度」でもありません。
それは、企業が社員のキャリアと人生に、どこまで寄り添うのかという姿勢を示す、極めて象徴的な報酬要素です。
制度を残すにしても、形を変えるにしても、大切なのはその意図を丁寧に言葉にし、社員と共有すること。
退職金の議論は、報酬制度の話であると同時に、企業文化そのものを見つめ直す機会なのだと感じています。
人事コンサルティングについての各種サービスお問い合わせはこちらから